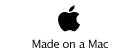My Blog
私の目標は、皆さんに『研究の面白さ』を知ってもらう事! そのためには、自分に興味持てる事に取り組んでもらいたい!
そこで、古川研では、大学生/院生でも理解できるレベルの物理(直感的にその現象が理解できるもの!)の研究テーマをいくつか提案させて頂き、
その中から、学生さん自身に、自分の興味にそった課題を選んでもらうところから研究を開始しています。
直感物理と言っても取り上げる課題のほとんどは、その研究成果が、そのまま学術論文にできるレベルのものがほとんどです。
課題が決まったら、まず、その物理の基礎的なことを勉強してもらいます。
もちろん、最初は、慣れない物理用語ばかりで焦ることもあるようですが、段々と慣れて使えるようになります。
(それは、先輩たちの様子を見れば理解できます。)そして、自己の研究テーマについて
『何が問題で、それをどうやって解決していくか。そのために何から始めなければいけ ないか』
を理解してもらいます。
また、できるだけ早い段階から試料作成に挑戦します。(試料作成をしない人もいます。)
そして、試料が準備出来次第、その物性を測定していくことになります。
基本的な機械操作等になれたら、そのあとは、
『何をどうしたら、どうなって。何がわかって。何がわからなくて。次に必要な情報は 何で、それをどうやって手に入れるか。』
自身の創意工夫による進展を楽しみながら積極的に研究を進めてもらいます。
もちろん、こちらからもフィードバックをできるだけ何回もかけます。(その回数は学生さんのやる気に比例します。)
古川研では、自称『古川研中間発表会』を年に数回行います。一回目は、全員が自分の研究の内容紹介をパワーポイント等を活用し行います。
学生さんが5人いれば、5テーマ。独立した内容ですので、ここで、しっかりと他の人の研究テーマを理解してもらいます。
そして、2回目以降の発表会では、それまでの研究成果と今後の課題などについて、個々の研究の進捗状況を報告してもらいます。
この発表会のいいところは、すべての疑問を解決するまで話し合い、理解するまでがんばるところです。
時に、一人の発表の時間が半日に渡ることもありますが、必要であれば理論式や装置の測定原理に戻ったりしながら、
何をどう勉強すればいいのかまで、その場で解決するので、結局のところ早道かなと思っています。
(また、怖い先生(私)の質問に対し、いかに論理的に反論するか、ディベート道場の役割も担っています。)
大学院に進学した人のほとんどが、その研究成果を、日本物理学会、日本中性子科学会、そして種々の国際会議で発表しています。
会議録の論文(英語)を書く人も多くいます。2006年度は、4年生の9月に日本物理学会で研究報告した人もいました。
(その内容、頻度は、研究成果のページを参照してください。)
学会発表/準備は、とても大変なことです。それでもみんながんばってくれました。また、『いい経験だった』と言ってくれました。
私は、古川研に来る人たちには、根気と根性を求めます。それは、『がんばれば、できる。』を実証したいと思っているからです。
毎日、何か1つのことをこつこつがんばれば、その道のプロになれます。その過程から、自分の存在意義を見いだして欲しいと思っています。
また、創意工夫して得られた結果を自負して欲しいと思います。
『こういう風にやった。だめだった。で、違う方法を考えた。今度は、うまくいった』
人生そう言うことを繰り返していくものです。そして、その向上心が生き甲斐を産んでいくのだと思います。
そして、それが「研究って、面白い!」につながって行く事を望んでいます.

2010年3月17日水曜日
古川研を目指す人へ